10月2日にCuleafも8歳を迎えます。創業◯年祝い!と、毎年、家族とも会社でも祝わないですが、毎年10月を迎えるとひとりで創業時のことを思い返してしまいます。
「松井くん!この世の中、やる人間かやらへん人間か、どっちかやで!」
とサラリーマン時代の私の心にズシっと突き刺さる言葉を残してタクシーに乗り込み、品川のホテルに帰った原田隆史先生。あの言葉がなかったらCuleafはなかったと今でも回想します。
学生時代に学習塾ZERO-GRAVITYを立ち上げ、将来は「寺子屋事業をする!」と誓っていた私は、メーカーや金融の営業職に没頭しながらも、
「これからの日本は子どもの教育しかない!」
と、飲みに行けば偉そうに語っていました。そんな教育に対する熱くるしさを見かねてか、知人がカリスマ中学教師として有名になり、コンサルティング会社を立ち上げていた原田隆史先生の勉強会に誘ってくれました。勉強会の終わりに、皆で飲みに行くことになり、教育現場のこともろくに知らない私が、
「今の公立の先生はダメですよね。」
とか、
「日本の教育制度はダメですよね。」
と、原田先生からすると聞き飽きたような問題提起ばかりしてしまいました。そうしたとき、原田先生から
「松井くん、公立の先生も捨てたもんじゃないぞ!私の勉強会に金曜日の夜にきて夜中の2時まで勉強をして、そこから和民にいって5時まで飲んで、そのまま土曜日の授業にいく先生だってたくさんいる!」
と一喝されたことを強烈に覚えています。
その後、先生のお話をいろいろとお聞きしたあと、
「松井くん、この世の中やる人間か、やらへん人間か、どっちかやで!」
とタクシーに乗る間際に私に言い残してくれたのです。
きっと、私のように教育論をうるさく語る評論家は原田先生の周りに少なくなかったのでしょう。そこで、
『結局、お前はやる人間になれるのか?』
と様々な思いを込めて残してくださったのだと思います。
「世の中にないものを創ろう!」
との創業の思い、教育に対する思いは変わりません。
ただ、まだ「やる人間」になれていない気もします。
「よりよくする」
という経営理念で、Culeaf、SPAMO、GABBY、ZEGRAも改善して参ります。
9年目にもご期待ください。
Culeafグループ まつい
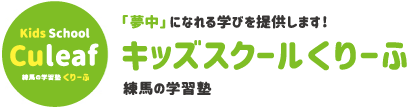






最近のコメント