私は子どもたちが一生懸命に頭を使って考えている姿が大好きです。表情を見ているだけでも頭の中の思考の様子が浮かんできて、「もっと考えろ!思考しろ!」と心の中で応援しています。
そんな子どもたちを見ていると、ふと気になることがあります。
①鉛筆が短すぎる、②鉛筆の芯が硬すぎる、③消しゴムが小さい、④消しゴムにカバーがない、など筆記用具に関してです。
子どもたちの勉強道具はしっかりと準備しておくことが大切です。鉛筆に関しては、短いと鉛筆の持ち方が崩れますし、鉛筆で書ける範囲が狭まり、手の動きが大きくなります。当然その分だけ疲れが増します。短すぎる鉛筆は交換、または補助軸をつけてあげてください。芯の硬さは、小学生の間は「B」または「2B」程度の芯を選ぶのがいいです。硬すぎると消しても消えません。シャーペンを使用する場合は、細すぎる、太すぎるものを選ばないように注意してあげてください。消しゴムに関しては、よく消えるものを用意してあげてください。カバーはしっかりとつけて、消しゴムが小さくなってきたら、カバーも切っていきましょう。
使い勝手がいい文房具はストレスを軽減させられます。子どもたちにとって毎日使うものですので、たまに筆箱の中を見て、チェックしてあげてください。
キッズスクール マネージャー 中桐 義博
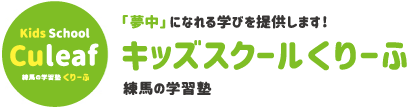






最近のコメント